数学ってどこで使うんでしょうね。数ⅠⅡⅢに数AB。新課程で追加された数C。計6科目。なかなかに大変ですよね。数学の勉強で得られることについて解説してみます。
トピック
- 日常編:こんな時には数学の知識を
- 研究編:”あの解き方”を覚えておけば…
- 思考力:証明問題や関数の問題で鍛える
- 応用編:数学は科学を進展させるために生まれた
- まとめ
日常編:こんな時には数学の知識を
買い物の時に10円のお菓子を10個買って10+10+10…をする人っていませんよね。10×10=100で終わらせるはずです。この要領で日常に数学を落とし込んでみましょう。文化祭を例にとってみましょう。
文化祭①…クラスの出し物でアトラクションを作るとき、まさか行き当たりばったりでつくりませんよね。設計図を書いて全員に共有していると思います。場合によっては四角形の対角線上に木をはめることもあるかもしれません。ここで数学を使いましょう。三平方の定理から√の近似値をとれば簡単に求まります。
文化祭②…食べ物の値段をどうしようか迷いませんか。収益を上げたいが、売れ残りは嫌だ。こんな時に使うのが、線形計画法です。詳しくは省きますが、一次関数の組み合わせで最適な値段を求められます。(現実はそう単純じゃないんだけど…)
研究編:”あの解き方”を覚えておけば…
これは大学教授がおっしゃった話です。研究をするうえで「それ、あの時の数学の解き方が使える形じゃん」となるケースがあります(あるそうです)。知っている人はすぐに気づけて、知らない人や適当にやっていた人はずっと気づけない。教授曰く、大学数学は気づければよいとのことですが、中学・高校の過程は確実に解けるようになっておきましょう。
思考力:証明問題や関数の問題で鍛える
学生嫌い率top常連の証明問題と関数です。ですが、思考力とりわけ、問題を解くには何が必要でそのために何をすればよいか考える能力が身につきます。ここで鍛えた思考力が、数ⅢCで後々効いてきます。別枠で、本を読んでおくと読解力が上がるので、このあたりの分野を楽に進められます。
応用編:数学は科学を進展させるために生まれた
そもそもの数学は、物理や化学の分野の計算をするために生まれた経緯があります。例えば、速度や加速度を求めるために微分・積分したり、pHを求めるためにlogをとったり。これらを考えるときに、新たな概念として生み出す必要があったわけです。微積やlogの話が気になる人は、数Ⅲと専門の物理化学を履修して、Let’s理系です。
まとめ
数学をいろいろな面で考えてみました。日常にも研究にも、潜在的に転がっています。直接気付きにくいところで役に立っています。何をするにも基礎が大事なので、これから勉強する人は焦らずに数IAから始めましょう。
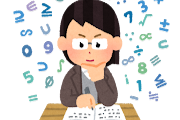


コメント